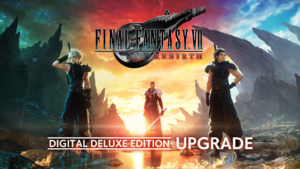「Xbox」の名を冠したASUSの携帯ゲーミングPC、「ROG Xbox Ally」。その登場は多くのゲーマーの期待を集めましたが、同時に大きな混乱も生み出しました。特にその「価格設定」と「スペック」について、一体MicrosoftとASUSのどちらが主導権を握っているのか、不透明な状況が続いていました。
多くのユーザーが望んでいたのは、「Xboxブランド」を冠するからには、Microsoftによる戦略的な価格設定(つまり、ハードウェアのコストを補助した、より安価な本体)だったのかもしれません。
しかし、発売日を過ぎてもなお燻る(くすぶる)これらの疑問に対し、ついにXboxのトップが口を開きました。Xbox社長サラ・ボンド氏が米Variety誌のインタビューで語った内容は、この混乱する状況を整理すると同時に、ゲーマーが抱いていた「淡い期待」を打ち砕くものでした。
この記事では、ボンド氏の発言から明らかになったROG Allyの価格設定の裏側と、なぜ私たちが期待した「安価なXbox携帯機」にはならなかったのか、その理由を深く考察します。
記事の内容を音声で聞きたい方はこちら↓
※今回は少し分かりにくいお話なので、音声の方が理解しやすいかもしれません。

1. 明確になった価格決定権「決めたのはASUS」という事実
ゲーマーの間で最大の謎だった「価格は誰が決めたのか」。これに対し、サラ・ボンド氏は明確に回答しました。
ボンド氏は、ASUSがWindowsゲーミングハンドヘルド市場で培ってきた経験を尊重し、Microsoftは「デバイスの最終価格決定」をASUS側に委ねたと説明しました。
これは、ROG Xbox Allyが「Microsoft製品」ではなく、あくまで「ASUS製品」であることを明確に示すものです。
Xboxのロゴが付けられているのは、OS(Windows 11)とGame Passというプラットフォームを提供するMicrosoftとの「パートナーシップの証」ではありますが、製品の製造コスト、スペック構成、そして最終的な値付け(メーカー希望小売価格)に関するビジネス上の決定は、ASUSが単独で行った、というのが今回の発言の核心です。
この結果、2つのモデルが提示されました。
- $999.99 ROG Xbox Ally X
Ryzen AI Z2 Extremeプロセッサを搭載し、パフォーマンスを最優先する層に向けたハイエンドモデル。 - $599.99 ROG Xbox Ally
より価格を抑え、カジュアルに楽しみたい層に向けたスタンダードモデル。
ボンド氏自身は、これらの価格設定はターゲット層にとって「価値のある製品だ」と擁護していますが、市場の反応は必ずしもポジティブなものばかりではありません。
2. 補助金はなかった。Gamescomで噂された「逆ザヤ戦略」の夢
では、なぜ多くのゲーマーはもっと安い価格を期待してしまったのでしょうか。それは、従来のゲーム専用機ビジネスの「常識」にありました。
家庭用ゲーム機(コンソール)の世界では、メーカーがハードウェアの販売で意図的に損失を出し(いわゆる「逆ザヤ」)、その赤字をゲームソフトの売上やサブスクリプションサービス(Xboxで言えばGame Pass)で回収する、というビジネスモデルが一般的です。
Gamescomでの価格発表が遅れた際、一部では「Microsoftがコストの補助を検討しているのではないか」という噂が流れました。もしMicrosoftがROG Allyのコストを一部負担すれば、$599.99のモデルはさらに競争力のある価格で市場に投入できたはずです。
しかし、残念ながらその期待は実現しませんでした。ボンド氏の発言は、裏を返せば「MicrosoftはROG Xbox Allyのコストを一切負担していない」ことを意味します。
ASUSはPCメーカーとして、ハードウェア単体で利益を出す必要があります。その結果、価格はゲーマーの期待よりも「高い」ものとなったのです。

3. ユーザーの不満と疑念「高すぎる」「Xboxゲームが全部動かない」
このASUS主導の価格設定は、いくつかの深刻な批判を生んでいます。
第一に、純粋な価格への不満です。特に$599.99のスタンダードモデルですら、「その性能にしては高すぎる」という批評家の声は少なくありません。
第二に、「Xbox」を名乗りながら、すべてのXboxゲームが(ネイティブで)起動できるわけではないという互換性の問題です。
これはWindows 11搭載機である以上避けられない側面もありますが、「Xbox」のブランドを信じて購入したユーザーにとっては裏切りとも映りかねません。
さらに、予約販売の状況も混乱に拍車をかけています。パフォーマンス重視の$999.99モデルはMicrosoft Storeで完売するなど好調に見えますが、一部のゲーマーからは「メーカーが意図的に供給量を絞っているのではないか」という「品薄商法」への疑念まで浮上しています。

4. それでも「X」は売れる。そしてMSは「次」を見ている
$999.99という高額にもかかわらず、「ROG Xbox Ally X」は競合するほとんどの携帯型ゲーム機を凌駕する性能(Ryzen AI Z2 Extreme搭載)を誇ることも事実です。パフォーマンスを金で買うことを厭わない(いとわない)ハイエンド志向のゲーマーにとって、これが魅力的な選択肢であることは間違いありません。
では、Microsoftはこの状況をどう見ているのでしょうか。
ボンド氏は、互換性のギャップを埋めるために「エミュレーション」を採用する可能性を示唆しつつ、最も重要な点として、「Microsoftが新しいXbox本体を自社で設計している」ことを改めてファンに保証しました。
つまり、ROG AllyはあくまでASUSとの「協業」であり、Microsoftの「本命」は別にある、ということです。
ただし、その「本命」が従来の据え置き型ゲーム機になるかは未知数です。AMDが開発の主導権を握っているとの報道もあり、Microsoft自身がどのような形の次世代機を構想しているのか、引き続き注視が必要です。
まとめ
今回のサラ・ボンド氏の発言により、ROG Xbox Allyをめぐる混乱の多くは解消されました。このデバイスは「Microsoftが作った携帯機」ではなく、「ASUSが作り、MicrosoftがOSとプラットフォームを提供するPC」だったのです。
価格決定権がASUSにあった以上、従来のゲーム機のような戦略的な価格設定(補助金による低価格化)が望めなかったのは当然の帰結でした。
この一件は、私たちゲーマーに「Xbox」というブランド名を冠する製品への「期待値」を、改めて考え直させる機会を与えたと言えるでしょう。$999のハイエンドモデルが示す圧倒的な性能を選ぶのか、それとも、Microsoftがいつか出すかもしれない「自社製の本当のXbox携帯機」を待つのか。
ROG Xbox Allyは、良くも悪くも、MicrosoftとPCメーカーとの協業の「限界」と「可能性」の両方を示した試金石として、記憶されることになりそうです。