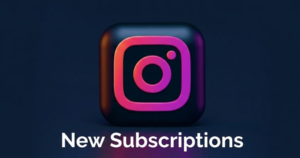スマートフォンの世界地図が、静かに、しかし確実に塗り変わろうとしているのかもしれない。私たちの手の中にあるこの小さなデバイスは、単なる通信機器ではなく、今や国家間の技術覇権争いの最前線でもある。
そんな中、中国のテクノロジー巨人たちが、AndroidとiOSという二大巨頭が築き上げた牙城に風穴を開けるべく、水面下で壮大な計画を推し進めているという情報が駆け巡っている。Xiaomi、Huawei、そしてOppo、Vivo、OnePlusを擁するBBKグループ。
彼らが目指すのは、米国の影響を完全に排した「独立OS」の確立だ。この動きは、単なる企業戦略を超え、世界のテクノロジー秩序を揺るがす地殻変動の前触れなのだろうか。
記事の内容を音声で聞きたい方はこちら↓

なぜ中国企業は「Google離れ」を急ぐのか

この壮大な構想の引き金となったのは、言うまでもなく激化する一方の米中間の地政学的緊張である。特に、ドナルド・トランプ前大統領の政権下で顕著になった、そして再燃の可能性も囁かれる米中貿易摩擦は、中国のテクノロジー企業に「Googleなしの未来」を真剣に検討させる強烈なインセンティブとなった。
思い出されるのは、2019年のファーウェイに対する米国の制裁だ。具体的な証拠が十分に示されないまま「国家安全保障上の脅威」とされ、エンティティリストに追加されたこの一件は、中国のテクノロジー業界全体に衝撃を与えた。Googleモバイルサービス(GMS)の使用が事実上禁止され、一時は世界市場からの撤退も囁かれたファーウェイ。この苦い経験は、米国技術への依存が、いかにビジネス上の致命的なリスクとなり得るかを痛感させた。
この教訓から、中国のテクノロジー大手は、単に制裁を回避するための一時的な戦術としてではなく、より根本的な「デジタル主権」の確立へと舵を切り始めた。その核心にあるのが、OSというソフトウェアの根幹から、アプリストア、クラウドサービス、さらには決済インターフェースに至るまで、ソフトウェアサプライチェーン全体を自国の管理下に置こうという戦略だ。それは、米国の制約から完全に自由な、独自のデジタルエコシステムを構築するという、壮大かつ困難な挑戦なのである。
複数の情報筋によると、XiaomiはGoogleサービスなしで動作する「HyperOS 3」の代替バージョンを開発中だという。これは、ファーウェイやBBKエレクトロニクス(Oppo、Vivo、OnePlusの親会社)といった他の巨大企業も巻き込んだ、より広範な戦略の一環と見られている。BBKグループもまた、Googleサービス、ひいては米国の特許からも自由なOSの開発を計画していると報じられている。この動きは、まるで静かなる革命の狼煙のようだ。
先駆者ファーウェイのHarmonyOSが示した可能性

この「脱Android」の動きにおいて、ファーウェイの存在は極めて大きい。同社が開発したHarmonyOSは、まさにこの戦略の試金石であり、後続企業にとっての道標ともなっている。
当初、HarmonyOSはAndroidオープンソースプロジェクト(AOSP)をベースとしていた。しかし、最新版とされる「HarmonyOS Next」では、Androidのコードベースから完全に脱却し、独自のカーネルとシステムコンポーネントで構築された、真に独立したプラットフォームへと進化を遂げたとされる。この大胆な転換は、技術的な困難さを伴う一方で、「米国の影響を完全に排除する」という強い意志の表れだ。
そして、この戦略は中国国内で驚くべき成功を収めつつある。報道によれば、HarmonyOSは2024年中に中国国内でiOSを抜き、Androidに次ぐ第2位のスマートフォンOSになる見込みだという。これは、強力な国内市場と政府の後押し、そして何よりもファーウェイの不屈の努力が結実したものと言えるだろう。
この国内での成功を足がかりに、ファーウェイは野心的な国際展開も視野に入れている。2024年にスマートフォンとタブレット向けにHarmonyOSを展開し、2025年にはスマートスクリーンや車載システムへも拡大。そして、2026年には満を持して国際市場に本格参入し、Androidと真っ向から勝負を挑む計画だと伝えられている。これが実現すれば、長らく続いたモバイルOSの二大独占体制に、本格的な地殻変動が起こる可能性がある。
しかし、ファーウェイの道のりは決して平坦ではなかった。そして、この経験は、後に続く中国企業にとっても重要な教訓を含んでいる。特に、ソフトウェアの独立と並行して進めなければならないのが、ハードウェアの国産化という、もう一つの大きな課題だ。
ハードウェアというアキレス腱

中国メーカーは、ディスプレイやカメラセンサーといった部品に関しては、国産品を調達できるようになってきている。しかし、スマートフォンの頭脳であり、性能を左右する最も複雑なコンポーネントであるSoC(System-on-a-Chip)に関しては、依然として米国およびその同盟国の技術に大きく依存しているのが現状だ。
ファーウェイ傘下のHiSiliconが開発していたKirinチップは、米国の制裁により最先端の製造プロセスへのアクセスを絶たれ、大きな打撃を受けた。その後、中国国内のファウンドリ(半導体受託製造企業)であるSMICなどが一定の進歩を見せているものの、TSMCやSamsungといった世界のトップランナーにはまだ技術的な差があると言わざるを得ない。
OSを独自開発できたとしても、それを快適に動作させる高性能なSoCを安定的に調達できなければ、競争力のあるスマートフォンを生み出すことは難しい。このハードウェア、特に最先端半導体の確保という課題は、中国企業が「完全な独立」を達成する上での最大のアキレス腱の一つと言えるだろう。この問題の解決なくして、真のデジタル主権はあり得ない。
独立エコシステム構築という「超巨大プロジェクト」
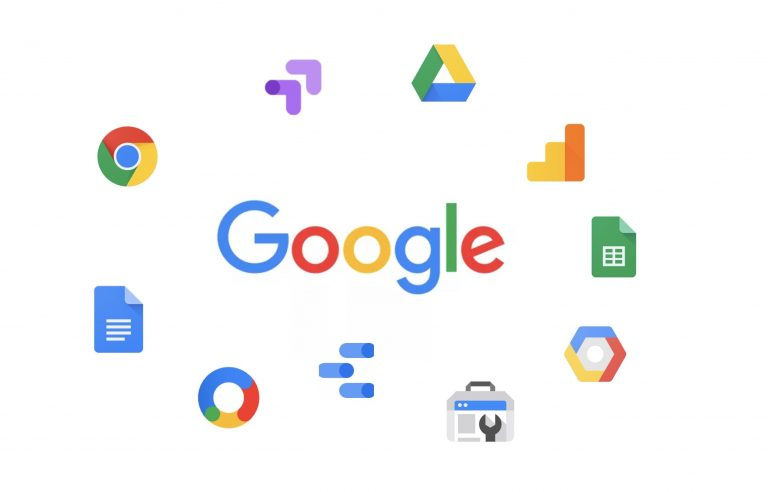
仮に技術的な課題をクリアし、高性能な独自OSとSoCを開発できたとしても、それだけでは成功は約束されない。モバイルOSがユーザーに受け入れられるためには、魅力的で多様なアプリケーションエコシステムの構築が不可欠だからだ。
これが、AppleがiPhoneとApp Storeで長年かけて築き上げ、今もなお業界で例外的な地位を保っている理由の一つである。ユーザーはOSそのものを使っているというよりは、その上で動く無数のアプリを通じて便益を得ている。ゲーム、SNS、金融、仕事、エンターテイメント…これらを提供するアプリがなければ、どんなに優れたOSも「宝の持ち腐れ」となってしまう。
Xiaomiとそのパートナーたちが、この「エコシステムの壁」を乗り越えるためには、いくつかの巨大な障害が立ちはだかる。
- Googleサービスの代替
特に欧米市場においては、Googleマップ、Gmail、YouTube、そして何よりもGoogle Playストアといった、生活に深く根付いたサービスに代わる、信頼性と利便性を兼ね備えた代替手段を提供する必要がある。これは技術的にも、ユーザーの習慣を変えるという点でも至難の業だ。 - 既存ユーザーの離反リスク
長年Googleのエコシステムに慣れ親しんだ膨大な数のユーザーが、新しい、未知のエコシステムへスムーズに移行してくれる保証はない。データ移行の煩雑さ、使い勝手の違い、そして何よりも「慣れ親しんだアプリが使えないかもしれない」という不安は、大きな離脱要因となり得る。 - 開発者の誘致
魅力的なアプリを揃えるためには、世界中のアプリ開発者に、新しいOS向けにアプリを開発・提供してもらう必要がある。しかし、iOSとAndroidという巨大プラットフォームが既に存在する中で、第3のOSに開発リソースを割いてもらうためのインセンティブをどう提供するのか。開発ツールの整備、技術サポート、そして何よりも収益化の道筋を示す必要がある。 - グローバルなアプリの利用可能性
中国国内で人気のアプリが、必ずしもグローバル市場で受け入れられるとは限らない。逆に、グローバルで人気のアプリが、中国発の新しいOSですぐに利用可能になるかも不透明だ。この「アプリの分断」は、ユーザーにとって大きな不利益となる。 - 莫大な投資
これら代替サービスの開発、エコシステムの構築、そしてグローバルなマーケティングには、想像を絶する規模の資金と時間、そして人材が必要となる。
こうした背景から、Xiaomiが開発中とされるGoogleフリー版のHyperOS 3は、現時点ではあくまで「戦略的予備」として位置付けられているようだ。つまり、万が一の事態に備えた保険であり、当面は欧米市場向けにGMSを統合した「フルバージョン」も並行して提供し続ける戦略を取ると見られる。これは、現実的なリスクヘッジと言えるだろう。
過去の失敗は繰り返されるのか?チャレンジャーたちの墓標

歴史を振り返れば、AndroidとiOSの二大巨頭に挑み、そして散っていったチャレンジャーは数知れない。
- AmazonのFire Phone (2015年撤退)
強大なEC帝国とクラウドサービスを持つAmazonでさえ、Google Playストアの欠如という壁を乗り越えられず、わずか1年で市場から姿を消した。 - SamsungのBada OS (2011年~)
当初は一定の成功を収めたものの、アプリ不足が響き、最終的にはAndroidへと軸足を移さざるを得なかった。 - Windows Phone (市場シェア3%未満で終焉)
MicrosoftとNokiaという巨大企業がタッグを組んだにもかかわらず、アプリエコシステムの貧弱さからユーザーの支持を得られず、歴史の闇に消えた。 - SamsungのTizen OS
スマートフォンでは失敗したが、その技術はスマートウォッチや一部のテレビで生き残っている。これは、特定のニッチ市場では独自OSが生き残る可能性を示唆しているが、汎用的なスマートフォンOSとしての成功は極めて難しいことを裏付けてもいる。
これらの失敗事例は、単に技術的に優れたOSを作るだけでは不十分であり、いかに強固なエコシステムを構築し、ユーザーと開発者を惹きつけるかが成功の鍵であることを、痛いほど教えてくれる。中国企業連合は、これらの「先人たちの墓標」から何を学び、どう活かすのだろうか。
中国ブランド連合は「第三極」を生み出すか?Appleの漁夫の利は?

Xiaomi、Huawei、そしてBBKグループ。これらの企業がもし本当に手を組むならば、世界のスマートフォン市場で無視できないシェアを持つ巨大な技術連合が誕生することになる。この連携は、いくつかの明確なメリットをもたらす可能性がある。
では、この中国発の「第三極」候補の動きは、既存の二大巨頭、特にAppleにどのような影響を与えるのだろうか。
一部のアナリストは、これがAppleにとって脅威であると同時にチャンスでもあると指摘する。もし中国企業連合の独自OSが中国国内でシェアを拡大すれば、Appleの中国市場における立場はさらに厳しいものになるかもしれない。中国政府が自国OSを後押しする政策を打ち出せば、その影響は計り知れない。
一方で、グローバル市場に目を向ければ、Androidエコシステムの「弱体化」あるいは「分断」は、相対的にAppleに有利に働く可能性もある。もし、これまでAndroid一択だったユーザー層の一部が、新しい中国製OSの登場や、それに伴う混乱を嫌気して、安定と高品質を求めるならば、その受け皿としてiPhoneが選ばれるシナリオも考えられる。
特にAppleのOSは、その閉鎖的な哲学ゆえにハイエンドセグメントに特化しているが、これはAndroidに近いオープンソースベース(あるいはその思想を受け継ぐ)の中国製OSとは異なるポジショニングであり、棲み分けが進む可能性もある。
なんか面白い話になってきましたね。あのXiaomi、Huawei、Oppoが手を組むとなると、購買層の多いミドルスペック帯のスマホやタブレットが、軒並み独自OSになると…想像しただけで恐ろしいですね。
しかし、今からAndroidの牙城を崩すのは、正直厳しいかもしれませんが、ここにSamsungが裏切ってくれれば、ワンチャン…