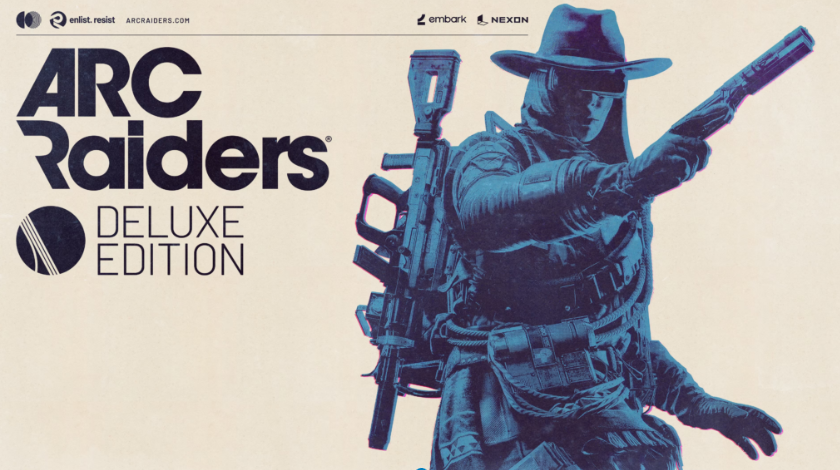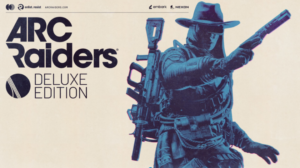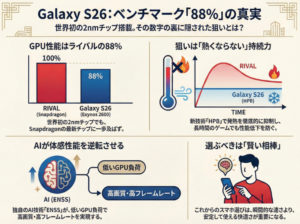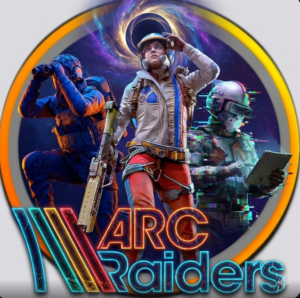「コントローラーが振動する」という体験が、初代PlayStationのDualShockで初めてもたらされた時の衝撃を覚えているでしょうか。
あれから数十年、振動は「ハプティックフィードバック」へと進化し、私たちはゲーム内の砂の感触や、弓を引き絞る重みを感じ取れるようになりました。
しかし、ソニーのエンジニアたちは、まだ満足していないようです。
最近、ResetEraフォーラムで発見された特許情報によると、ソニーはDualSenseの次なる進化系として、なんと「油圧システム」を検討しているといいます。電子機器の中に液体を入れる。一見すると正気とは思えないこのアイデアですが、読み解いていくと、そこには従来のモーターでは再現できない「リアルな感覚」への執念が見えてきました。
今回は、11月20日に公開されたばかりのこの特許文書をもとに、もしこの技術が実用化されたら私たちのゲーム体験はどう変わるのか、そしてユーザーが本当に懸念している「あの問題」はどうなるのかを深掘りしていきます。
Source:Nweon.com
記事の内容を音声で聞きたい方はこちら↓

振動から「流動」へ。モーターを捨てるという選択
まず、この特許の核心部分である「仕組み」について解説しましょう。
現行のDualSenseコントローラーには、振動を生み出すための「モーター」や「ボイスコイルアクチュエーター」が内蔵されています。これらがブンブンと回転したり振動したりすることで、私たちの手に感触を伝えているわけです。
ところが、今回の特許で提案されているのは、それらを「液体で満たされたリザーバー(貯蔵タンク)」に置き換えるという大胆な発想です。
具体的には、コントローラー内部にシリコンオイルのような液体が入った袋があり、ボタンやスティックへの入力に合わせて、この液体が移動したり、圧力を変えたりします。
特許文書には「周辺機器の可動部品を調整することで、ボタン、スティック、トリガーの動きに対する抵抗を調整できる」とあります。
これはどういうことかと言うと、例えばゲーム内でキャラクターが「泥沼」に足を踏み入れたとします。従来のコントローラーなら「ブブブ」と振動して歩きにくさを表現するでしょう。
しかし、この油圧システムなら、スティックを倒す指先に、まるで本当に粘り気のある泥を押しのけているかのような「重たくてヌルッとした抵抗」を物理的に作り出せるのです。

「冷たい雨」や「熱い銃身」も再現?温度変化という隠し玉
さらに驚くべきは、この液体システムには「温度調整」の可能性も含まれている点です。
特許には、よりリアルなフィードバックを得るために、内部の液体を加熱または冷却するという提案もなされています。もしこれが実現すれば、氷の世界を冒険している時はコントローラーが冷たくなり、激しい銃撃戦の後にはトリガーが熱を帯びるといった表現が可能になります。
これまでは「振動(触覚)」と「音(聴覚)」と「映像(視覚)」で没入感を作ってきましたが、そこに「温度」という皮膚感覚が加わるわけです。まさにVR体験を手のひらサイズに凝縮しようとする試みと言えるでしょう。
なぜわざわざ「液体」なのか?メリットとリスクの天秤
ここで冷静な疑問が湧きます。
「なぜそこまでして液体を使う必要があるのか?」と。
特許出願の文書によると、これには意外なメリットがあります。それは「軽量化」です。従来の磁気式や機械式の振動システムは、強力なものほど金属部品が多くなり、コントローラーが重くなりがちでした。しかし、液体と圧力制御のシステムであれば、構造をシンプルにし、全体の重量を軽くできる可能性があるのです。
しかし、私たちユーザーの視点からすると、どうしても無視できないリスクがあります。
そう、「液漏れ」です。
精密な電子回路の塊であるコントローラーの中で、もし液体が漏れ出したらどうなるか。想像するだけで背筋が凍ります。また、液体を加熱・冷却するということは、バッテリー消費も激しくなるのではないかという懸念もあります。ただでさえDualSenseのバッテリー持ちは「短い」と不満の声が多い中で、これ以上の電力消費は致命的になりかねません。

スティックの「ドリフト問題」は解決するのか
そして、多くのゲーマーが最も気にしているのが、悪名高い「ドリフト問題」です。スティックに触れていないのに勝手に視点が動いてしまうこの現象は、現在のアナログスティックが採用している機械的な接触部品の摩耗が原因です。
今回の油圧システムは、この問題を解決するのでしょうか?
特許の説明を見る限り、機械部品への依存を減らす設計変更が含まれているため、摩耗によるドリフトは改善される可能性があります。物理的な接触ではなく、液体の圧力変化をセンサーで読み取る方式になれば、理論上は耐久性が向上するはずです。
しかし、ソニーはこれまで、摩耗しない「ホール効果センサー」や「TMR技術」の採用には消極的でした。
高価なプロコンであるDualSense Edgeでさえ、従来型のスティックを採用しています。油圧システムが導入されたとしても、その構造が複雑怪奇であれば、今度は「修理が不可能に近い」という別の問題が発生するかもしれません。

技術のロマンと現実の狭間で
今回の特許情報を見て私が感じたのは、ソニーという企業の「遊び心」と「危うさ」の同居です。
普通の企業なら「バッテリーを長持ちさせよう」「壊れにくくしよう」という、ユーザーの不満を解消する方向へ進化を進めるでしょう。
もちろんソニーも交換可能なバッテリーなどの噂はありますが、それ以上に「誰も体験したことのない感覚を作りたい」というエンジニアの強烈なエゴ(良い意味での)を感じずにはいられません。
水と電気。本来相容れないものを融合させて、新しいゲーム体験を作ろうとする姿勢は、かつてウォークマンやAIBOを生み出したソニーらしさに溢れています。
もちろん、これが製品化されるまでには数年かかるでしょうし、もしかしたら永遠に発売されないかもしれません。それでも、「ただのボタン入力装置」だったコントローラーが、生き物のように熱を持ち、抵抗するデバイスへと進化しようとしている。その過渡期をリアルタイムで見届けられるのは、私たちゲーマーにとって一種の特権なのかもしれません。