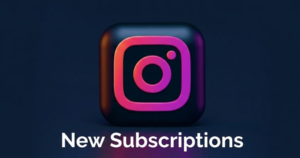TikTokやYouTubeショートをスクロールしていると、どこかで見たような映画の切り抜きに、無機質なAIナレーションと字幕がつけられた動画が、次々と流れてくる。そんな経験はありませんか?「これなら自分でも作れそう」「これで収益が生まれるの?」と、多くの人が一度は疑問に思ったことがあるはずです。
その”グレー”な領域に、ついにYouTubeが鉄槌を下します。
2025年7月15日、YouTubeは収益化ポリシーを大幅に更新し、「怠惰なAIコンテンツ」や「大量生産されたコンテンツ」に宣戦布告しました。これは、単なる規約の変更ではありません。プラットフォームの未来と、クリエイターエコシステムのあり方を賭けた、重大な方針転換です。
この記事では、あなたのチャンネルが”AI狩り”の対象にならないために知っておくべき全てを解説します。何が「アウト」で、何が「セーフ」なのか。そして、この変革の先に待つYouTubeの未来とは。すべてのクリエイター必見の内容です。
記事の内容を音声で聞きたい方はこちら↓

グレーコンテンツの氾濫に危惧したYouTubeが、ついに粛清を開始する?

何が変わる?YouTubeが掲げた「オリジナル」と「本物」への原点回帰
今回のポリシー更新の核心は、非常にシンプルです。YouTubeは、プラットフォームから「大量生産されたコンテンツ」と「繰り返しの多いコンテンツ」を排除し、クリエイターに対して、改めて「オリジナル(独創的)」で「本物(信頼性のある)」のコンテンツ制作を強く求める、というものです。
YouTubeは公式に次のように述べています。
「YouTube パートナー プログラム(YPP)で収益を得るために、YouTube は常にクリエイターに『オリジナル』かつ『本物』のコンテンツをアップロードすることを義務付けてきました。2025年7月15日、YouTube は大量生産されたコンテンツや繰り返しの多いコンテンツをより適切に識別できるよう、ガイドラインを更新します。この更新により、今日の『本物ではない』コンテンツの実態がより適切に反映されます。」
この声明から読み取れるのは、これまでも存在した理念を、現代のテクノロジー(特に生成AI)がもたらした状況に合わせて、より厳格に、そして具体的に適用していくという強い意志です。
これまで真摯に独自のコンテンツを作り続けてきたクリエイターにとっては、何ら影響のない、むしろ歓迎すべき変更でしょう。しかし、近年のAIツールの進化に乗じて、「楽して稼ぐ」ことを目指していた一部のクリエイターにとっては、まさに死活問題となり得るのです。
警告:収益剥奪の対象となる「怠惰なAIコンテンツ」の具体例
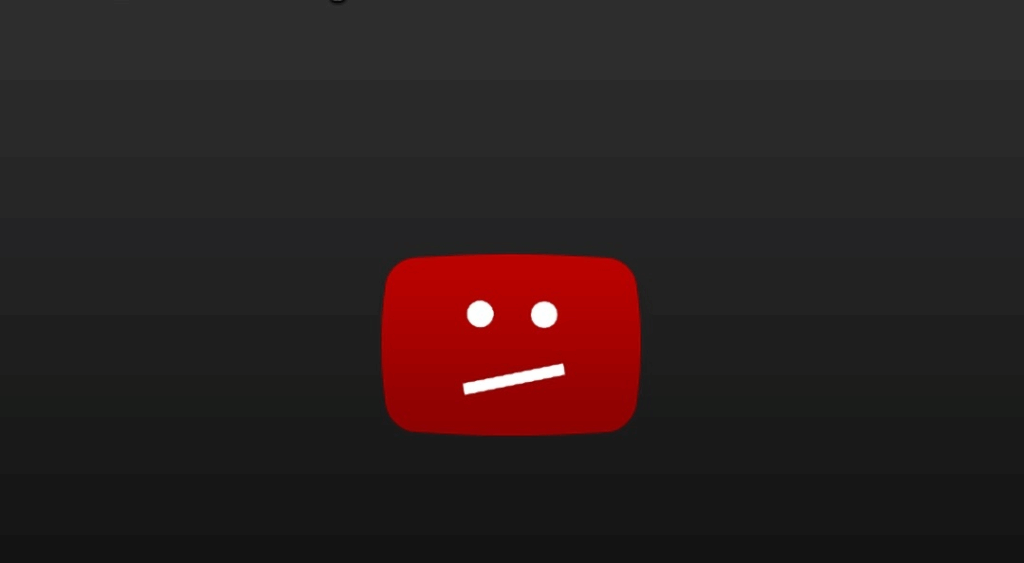
では、具体的にどのような動画が「大量生産されたコンテンツ」や「繰り返しの多いコンテンツ」と見なされるのでしょうか。YouTubeはまだ詳細なガイドラインを発表していませんが、提供された情報や現状から、規制対象となる可能性が高いのは以下のようなコンテンツです。
- 他人のコンテンツの安易な再利用
映画、アニメ、テレビ番組、または他のクリエイターの動画を無許可で切り抜き、それらを単につなぎ合わせただけのもの。 - テンプレート的なAI生成
最小限の編集や工夫を加えず、AIツールで自動生成したナレーションやBGM、映像をそのまま使用した動画。 - 独創性のないフォーマットの繰り返し
内容が僅かに違うだけで、構成や演出がほぼ同一の動画を大量に投稿する行為。
特に問題視されているのが、Redditなどのコミュニティでノウハウが共有されているような、いわゆる「顔のないAIコンテンツ」です。
これは、誰でも簡単に、そして短時間で動画を量産できる手法ですが、その本質は「他人の創造物の上前をはね、AIというツールで体裁を整えているだけ」と見なされても仕方ありません。カメラの前に立つのが苦手なこと自体は全く問題ありませんが、その解決策として、創造性を放棄し、安易な模倣や再利用に走ることは、YouTubeが最も嫌う行為なのです。
これらのポリシーに違反していると判断されたチャンネルは、最悪の場合、YouTubeパートナープログラム(YPP)から除外され、収益化の権利を失うことになります。
最大の懸念は「誤判定」のリスク。誠実なクリエイターは守られるのか?

YouTubeのこの決断は、長期的にはプラットフォームの質を向上させ、視聴者と誠実なクリエイター双方に利益をもたらすでしょう。しかし、多くの人が抱く最大の懸念は、その「施行方法」にあります。
一番怖いのは「厳選な審査を行わない、ガバガバな収益停止判定」です。
とはいえ、本物と偽物を見極めるのが極めて困難なほど、AI技術は進歩していますからね、、一番怖いのはガバガバ判定で、オリジナル動画でも誤って収益停止処置をされてしまい、多くのクリエイターが撤退してしまうことだけは、避けたいですね。
これは、決して杞憂ではありません。AI技術は日進月歩で進化しており、人間が作ったものとAIが生成したものの区別は、ますます困難になっています。YouTubeがどのようなアルゴリズムや人的リソースを使ってこれらのコンテンツを審査するのか、その詳細はまだ不透明です。
もし、この判定システムが不完全であれば、独創的なアイデアでAIツールを「補助的」に活用しているクリエイターや、たまたまテンプレート的に見えてしまう演出を用いたクリエイターが、不当に「怠惰なAIコンテンツ」と誤判定されてしまうリスクが生まれます。
一度でも収益化を停止されれば、クリエイターの活動意欲は大きく削がれます。本来守られるべき才能が、不透明なルールの下でプラットフォームから去ってしまう。それこそが、今回のポリシー変更における最大のリスクであり、YouTubeが絶対に避けなければならない事態です。

まとめ
YouTubeが「怠惰なAIコンテンツ」に宣戦布告した今回の決断は、コンテンツ飽和時代におけるプラットフォームの健全性を保つための、痛みを伴うが「必然的な一歩」だと私は考えます。
忘れてはならないのは、AIはあくまで「ツール(道具)」であり、それ自体に善悪はないということです。包丁が素晴らしい料理を生み出すこともあれば、人を傷つけることもあるように、AIもまた使い方次第です。クリエイター自身のアイデアや哲学、労力を「補助」するためにAIを使うのか。
それとも、創造のプロセスそのものをAIに「代替」させてしまうのか。2025年7月以降、その差がクリエイターの明暗を明確に分けることになるでしょう。
結局のところ、YouTubeというプラットフォームの価値は、「そこでしか見られない独自のコンテンツ」と「そこでしか出会えない魅力的なクリエイター」によって支えられています。今回の規制強化は、その原点に立ち返るための強い意志の表れです。
私たちクリエイターは、この変化を単なる「規制」や「危機」と捉えるのではなく、自らのコンテンツが持つ「独創性」や「本物である価値」を改めて見つめ直す絶好の機会と捉えるべきなのかもしれません。
今後数週間以内に発表されるという、YouTubeからの詳細なガイダンスを注視しつつ、私たちは自らの創造性と真摯に向き合っていく必要がありそうです。